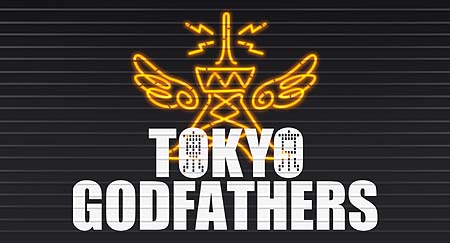決算2002-48
2002
年4月半ばに、前年より抱えていた「東京ゴッドファーザーズ」のコンテがアップした。全920カットほど(欠番を合わせると全部で945カット)を描くの
に、一年近くかかったであろうか。予想以上に時間がかかってしまったが、たいへん面白くなったと思っている。コンテだけでも面白いはずだが、フィルムにな
ればもっともっと面白く、音が付けばより一層面白いに違いない。
今回の「東京ゴッドファーザーズ」はこれまでの作品と趣が異なる。まずコメディである。多分。
おかしいのか悲しいのか、「不幸なんだか幸福なんだかよく分からない」というテイストを目指している。「滑稽な悲劇、切ない喜劇」というと高尚すぎる
が、割り切れない何かそういうものを表現できたら、と願っているが、どこまで実現できているのか、私も完成を見るまで分からない部分も多い。完成してもよ
く分からないかもしれないが。
ともかく、敵対する相手を倒してめでたし、といった単純で危険な価値観では作ってはいない。
「パーフェクトブルー」「千年女優」、これまでの2作品ともっとも大きく異なるのは、キャラクターの芝居を作品の重要な柱にしていることであろう。
もちろんこれまでの2作品でも芝居は重要であったし、それを疎かにしたつもりもない。ただ作品の成り立ち自体が異なるのである。前2作は、あくまで「物
語るための芝居」が大半を占めている、といっていい。シナリオにしろ絵コンテにしろ、そういう作りになっているし、そう目指していた。
前2作の場合、あくまで極端な話だが、キャラ芝居がもし通り一遍の凡庸な芝居であろうが少々拙かろうがそれぞれ作品として成立するように絵コンテを設計
していたつもりである。「芝居で持たせる」というようなカットの作り方ではない。語弊が大きいが勘違いしないでいただきたい。実際2作品とも、そうしたつ
まらない芝居を排除するよう与えられた環境の中で出来る限りのことはしてきたし、出来上がった作品においては、想定以上に豊かな芝居が数多く見られる。拙
い演出をキャラ芝居がカバーしてくれている部分は多い。
前2作におけるコンセプトの一つは、テレビアニメレベルの作画でも何とか面白く見られる物語、ということであった。無論テレビシリーズよりは遙かにコストも枚数も手数も才能もかかっているが、ともかく予算の制限による部分が大である。
現在のテレビシリーズの予算は一本あたり1000万〜1500万程度であろうか。無論もっと予算が出ているシリーズもあるが、ここでは仮に1500万と
しよう。シリーズ本篇分一本20分と想定すると、「パーフェクトブルー」(当初予算1億、エンディングを除いた本篇を77分として)が20分あたりで約
2600万。「千年女優」(当初予算1億3千万、本篇82分として)が20分で3200万。
単純に予算から考えれば「パーフェクトブルー」でテレビシリーズの1.7倍、「千年女優」で2.1倍程度の内容しか出来ないのである。
なのでシナリオを練り、コンテ演出で芝居を制限して、かける動画枚数を抑え、コストパフォーマンスの向上を狙っていたといえる。繰り返し断っておくが、深く関わってくれるスタッフの技量を疑っていたからではない。
作品全体の規模との相談でそうしたコンセプトとなったのである。しかし、それでも想定以上に大変な作業となったのは監督の拙さのせいである。
今回「東京ゴッドファーザーズ」において劇的に規模が大きくなったわけではない。私のギャラなんか「パーフェクトブルー」から据え置きなのだ。
だが芽生えた興味や欲求を抑えられるものでもないし、理性だけで作れるものか(笑)
芽生えた興味・欲求というのがキャラ芝居のことである。芽生えたのは「千年女優」においてである。「千年」のいくつかのカットにおいて見られた芝居に大変感じ入るところがあり、極端な話、それを拡大して一本の映画に出来ないか、と思い立った。
具体的に言えば、「千年女優」の大塚伸治氏や小西賢一氏などが担当してくれたシーンで、演出側としては思いもよらなかった「芝居」を見たことが「東京ゴッド〜」のコンセプトに大きく影響している。
語弊を承知で今回のコンセプトを平たく言えばこうなる。
「芝居そのものを見せ物に出来まいか」
かなり無謀と言っていい。
03.4.6
決算2002-49
「芝居そのものを見せ物にする」
より正しく言えば「芝居そのもの“も”見せ物にする」。
無論これは「芝居のための芝居」という意味ではない。
あくまで大雑把な印象だが、役者出身の監督の実写映画などで「芝居のための芝居」というシーンがよく見られるような気がする。演出する側が役者として心地良い見せ場を知っているが故に、つい見せすぎて冗長になってしまうのではないかと思える。
アニメーター出身者による演出にも同じケースがよく見受けられると思う。アクションをやりたいがためのアクションシーンなどがその典型であろうか。見て
いて微笑ましくなることもあるが、たいていは鬱陶しいことこの上ない。要するに、文脈にはまらないものを単なる好みではめ込み、あまつさえ拡大までする、
そうした作劇・演出を私は好まない。
そうしたある意味の「逸脱」や「暴走」が作品の大きな魅力を寄与することもあるので一概には言えないが、ただ、私が監督する場合には、そうした演出に陥
らないように注意しているというだけである。陥ろうと思っても陥れない性格なのではあるが。天秤座のバランス感覚ゆえの業だろうか。
もっとも、作画担当者の暴走にも似た強い欲求がある場合、それを魅力として取り入れることには吝かではない。ともすれば相反するような要請や欲求、意図の中でバランスを取り続けるのが監督と名の付くポジションの仕事であろう。
アニメーションにおける「芝居」という用語について触れておく。
大雑把にすぎるかもしれないが、アニメ業界では広義において絵を動かすことすべてを「芝居」と呼びならわしている、といっていい。
人物が演技することはもちろん、メカが飛ぼうが爆発しようが、パンツを見せるためにスカートをめくらせようが、ピンク色でハイライトだらけの髪の毛を揺らせようが、バレーボールみたいな巨大なお乳を振り回そうが、これらはみな「芝居」である。
「胸が揺れる芝居が固い」
などと、いい年こいた人間たちが口にする様はさぞや愉快であろう。そんな子に育つとは親も思っていなかったことであろうにな。
さてこの「芝居」。現在業界で流通しているその大半は「運動」という語に置き換えてもかまわないといえる。
「乳が揺れる運動が固い」
この通りである。しかしこれはどうだ。
「悲しむ運動が描けてない」
どんな運動なんだそれは。「日本全国悲しみ運動」とかそういう草の根運動か。
これはやはり「芝居」でなくてはなるまい。
日本のアニメーションはこの「芝居」と「運動」を混同したまま現在にいたってしまったのではないかと思われる。つまり、運動の再現こそが豊かな芝居であるといった認識が強いのではないか。
03.4.8
決算2002-50
「歩きの芝居が描けない」
という場合、通常これは運動を再現できていない、ということである。歩きや走りといった基本動作は難しいといわれるが、歩きや走りをきちんと描ける人は
多くない。右足前、左足後ろの絵、それと足が逆になった絵、この2枚の原画を描いて間に3枚でも4枚でも5枚でも動画(中割り)を入れれば、確かに歩いて
いるようには見える。ただ、それだけでは「歩いている」という記号にしか見えず、自然な歩き、というより自然に見える歩きにはなるまい。本来は見えなく
ちゃ困るし昔はそれで良かったらしいのだが、諸々事情があって、2枚原画ではまずまともな歩きにはならないことになってしまっているのが現状である。
余談だが井上俊之氏(「MEMORIES/彼女の想いで」作画監督などで知られるアニメーターの鑑)がこんな指摘をしていた。
「最近のアニメは歩きの歩幅が狭い」
井上氏が副作画監督をつとめていた「人狼」の折りに気が付いたそうだ。
なぜ歩幅が狭くなるかというとおそらく、歩きの基本ポーズである前後に足を大きく開いた状態が描きにくいからであろう。要するに描きにくいものは描かなくなる、と。人間は低きに流れるものであるよ。
日本のアニメでは一歩12コマ(0.5秒)の歩きが多用される。前後に足を大きく開いた状態(右前左後ろ、左前右後ろ)を2枚の原画として、その間にそ
れぞれ3枚の中間の絵を入れて、一枚を3コマ(3/24コマ−1秒24コマのフィルムの場合。ちなみにビデオは1秒30フレーム)で撮影するわけである。
間に入れる絵を4枚、5枚、7枚などにすると、絵の枚数分遅い歩きになる。略称して中4、中5などと呼ぶ。
多用される中3は1秒で2歩、歩くことになる。実際ストップウォッチを持って計りながら歩いたことがあるが、このペースはかなり早足である。私の場合なら終電を気にしながら駅へ向かうペースであろうか。
早足で歩くとスピードが増す分、本来歩幅は大きくなる。恐らく身長の半分くらいの歩幅になるのではないか。しかしそれだけ大きく足を前後に開いた絵は描
きにくいので、描きやすい程度に幅が狭くなり、歩幅の狭い一歩12コマのチャカチャカした歩きが多くなるのであろう。巨大な目玉のギャルアニメやギャグア
ニメならそれも成立するのかもしれないが、比較的リアルな頭身で、リアリティのある画面を目指す作品には不似合いなことこの上ない。
もっとも、最近の人たちの現実の歩きそのものが歩幅が狭くなっているようにも思えるので、そうした現実が多少反映しているのかもしれない。
「芝居」と「運動」の話に戻る。
運動がよく再現される、ということは画面上いかに「何でもないか」という、まさに「何でもないこと」に至る。このことがいかに重要でいかに難しいかはこ
の仕事に携わっている人間の中でも、かなり有能な部類の人ではないと実感できないと思われる。それを実感できている人間が多ければ現状のような惨憺たるア
ニメ映像が溢れるはずがない。
脚本やキャラクターデザイン、コンテ、レイアウトや原画動画、美術背景や色指定、撮影や編集そして声優さんの芝居や音響などなど、語弊を承知でいうが、どのセクションにおいてもいかに「何でもないか」を目指すものだと私は思う。
「何でもなく見える」というのは、「いかにその作品らしくあるか」ということだろう。それが一番の基本であり難しさともいえる。なので素人さんに「レイア
ウトが上手い」などと思われてしまうのはいかに「レイアウトが上手くないか」ということに繋がるのである。それぞれの制作過程はあくまで作品の一部、一素
材に過ぎず、作品とはそれらの総和よりさらに大きなものである。そうなっていてこそ作品といえる。
ともかくどれか一部が気になるほどに突出しているのは、魅力になることも多いが、バランスを崩しているという意味においては全体としてやはり上手くない
のである。もちろん意図的にバランスを崩して突出させる場合もあるので、そうしたアンバランスもバランスの一部である。
03.4.9
決算2002-51
たとえば単に「歩きを描く」といった場合、それは運動の再現をさすが、だからといって「歩くという芝居」が無論ないわけではない。運動の再現の向こう側に芝居があると言っていい。
漠然と「人が歩く」という運動を再現するのではなく、「他ならぬその人物が歩く」という観点こそが芝居に通じる。通じるのだが、そういうことを理解する
作画スタッフは業界には一握りしかいないのではなかろうか。さらにその芝居に複雑さと捻りを増せば、芝居を描けるスタッフはさらに少なくなる。そうした状
況をよく認識していながら、芝居の魅力に挑戦しようとすれば当然「無謀」の二文字が頭をよぎるのである。
しかし手を出してしまった。
そして案の定大変なことになってしまっている。
書き忘れていたが「芝居」と混乱される言葉に「段取り」というものもあろうか。合体して「段取り芝居」などという大変悪い意味の言葉に変化する。「段取り芝居」とは換言すれば「凡庸」ということに他ならない。
段取りを広辞苑で引くと「芝居などで、筋の運びや組立て」とあり、「事の順序・方法を定めること」ともある。カット内容における「段取り」というと、そのカット内において最低限必要なアクションを指すことになる。
たとえば「キャラクターが走って画面にイン、立ち止まってセリフを口にする」というのが「段取り」だとすると、そのキャラクターが「いかに走ってくるのか」、「いかに立ち止まるか」「いかに喋るのか」が「芝居」ということになろうか。
ここでいう「段取り」をこなすことが「芝居」と同一視されているケースが多いように思える。先の例でいえば、走ってくるキャラクターが焦っているのか、
軽い調子なのかといった程度のことはもちろん最低限描き分けられるものだが、その程度のことはやはり本来段取りに含まれるように思われる。しかし段取りを
こなしただけで芝居が出来ていると思う業界人が大半である。芝居は段取りのさらに向こうにある。
芝居というには「他ならぬその人物がそのシーンにおいてどう焦るのか」までを描かなければ最低限の芝居にもならないといっていい。
芝居とはどう運動するかとは違うし、段取りよりも上等であり、そしてそれは何より人物の表現である。時に運動の再現を無視してでも人物の表現がなされることもあり得る。
くどくどと説明しているわりに要領を得なくて申し訳ないが、何も面倒なことをいっているのではない。要はいかにその人がそれらしく描かれているか、とい
うことにつきる。いや、人に限ったことではないので、「いかにそれらしいか」、さらに理想をいえば「らしい」を越えて「いかにそれか」を描くことこそが目
的である。それはまだ私には随分先にあるように思えるので、現在は「いかにそれらしいか」が課題であろうか。
「いかにそれらしいか」ということであれば、これは何も動かす芝居だけにあるわけではなく、止め絵の一枚にも当然芝居はある。他ならぬその人物が特定の
シーンにおいて、どういう様で座っているのか、どう立っているのか、といった一枚の絵に雄弁な芝居がある。止めの絵だけで成立する漫画という表現で育って
きた私としては、止め一枚のポーズを疎かにすることには特に不快を覚える。
もっとも、人間が「ただ立っている」様を描ける人がほとんどいないのが現状で、そこに表現を求めても虚しい気持ちになるばかりである。棒立ち、という言葉があるが、「棒立ちの絵」を前にするとこちらが棒立ちになる。
こうしたケースはモブキャラなどの描写において特に顕著であろうか。主要な登場人物などは描き手も気にするので、なにがしかの意図が見えるが、モブの描
写などにおいては描き手のささやかな注意すら失われるようで、得てして「立ったように見える人の絵が描いてある」という程度の記号的な絵が目立つ。お里が
知れるのはこうした、ある意味「描き手がフラットな気持ち」で描いた場面であろう。絵を上手く見せかける努力すら失われたときに見えるもの、それが実力で
ある。いやぁ、他人事じゃないな、まったく。
とはいえ、人間が何でもなく立っている様を描くのは大変難しく、私もろくに描けないが。人が何でもなくそこに立っている様を何でもなく描けるようになりたいものである。
03.4.10
決算2002-52
「東京ゴッドファーザーズ」そのものの話題から流された。
さて、「芝居を見せ物にする」というコンセプトを違う言い方をすれば、キャラクターを見せることに大きな重心を置く、とも言える。
前2作のシナリオにおいては、いわば「構成」こそが命であり、シナリオは情動と論理のパズルのようであった。そのパズルの中を登場人物が約束に則って動
きさえすれば成立する、そうした考え方に立脚している。複雑なパズルに翻弄される気の毒な登場人物といえる。
従って、これまでの主人公二人、未麻にしろ千代子にしろ、いわゆるキャラクター性は非常に希薄である。脚本の村井さだゆき氏も監督の私も、キャラクター
描写に対する欲求がまことに少ない傾向にあるし、また前二作ではキャラクター性が希薄でなくてはならなかったとさえ言える。むしろキャラクターは作品全体
像で示される、というような考え方である。
「パーフェクトブルー」は、その物語や構成全体が未麻の心的内容を表しているように思えるし、「千年女優」の千代子はさらにその傾向が強い。
「東京ゴッドファーザーズ」はそうした物語や構成が主導するのではなく、登場人物のキャラクターによって生まれてくる物語をすくいとろうとしたシナリオと
言えようか。もちろん、私自身の構成好きともいえる傾向に大きな変化があるわけでもないので、そこは別な持ち味を持った人間に脚本をお願いすることで路線
を変更した。
信本敬子氏である。
信本とは実写「ワールドアパートメントホラー」(監督・大友克洋/脚本・信本敬子/原案・今
敏)の時に、少しばかり仕事をご一緒したが、基本的には飲み友達の間柄である。飲み友達で頼みやすいから脚本を頼んだ訳ではもちろんなく(多少そういう事
情もあるが)、ともかく大きな狙いがあってのことだ。
信本は私の傾向とは百八十度違うといってもよく、登場人物のパーソナリティにこそ比重を置くように思える。正直をいえば、信本の仕事をよく把握している
わけでもないのだが、仕事よりもその眼差しを信用したといえる。要するに信本は人間として信用できる、というようなこと。
そして、忙しい信本に共同脚本を引き受けてもらうためにこちらが用意した条件はこうである。
「プロットとか構成とか主なアイディア出しはこっちでやるからさ、キャラクター作ってよ」
いい加減な依頼の仕方だが、ぶっちゃけた話ができるのは飲み友達の強みである。実際、そんな話をしたのも吉祥寺の飲み屋においてだ。
「東京ゴッド〜」の最初のプロットは私が書いているが、これは企画書として出すために無理矢理でっち上げた面が強く、いざ本番のシナリオに向けてプロットを練り直す必要があった。
その頃、信本に聞いて驚いたことが一つ。
「私さぁ、プロットって書けないのよねぇ」
じゃあ、どうやってシナリオを書くですか!?、と私などはすぐに短絡してしまうのだが、おそらく彼女の場合は登場人物を書き込んで行くことで話の先が決
まって行くのだろう。だからプロットと思って書き始めてもシナリオに近い状態になるのであろうし、であるなら最初からシナリオとして書く方が性に合ってい
る、ということなのだろう。
登場人物のパーソナリティの側から考える信本と、構成とか展開といった登場人物たちを俯瞰する側から考えてしまう私。逆方向からのベクトルが出会う波打ち際に「東京ゴッド〜」がある、というと格好良すぎるが、概ねそういうイメージである。
信本のおかげで主人公の3人、ギンちゃん、ハナちゃん、ミユキは作品にとって大変魅力的な人物になったと思う。実際こんな人間が私の身近にいたときに魅
力を感じられるかどうかはまた別問題だが(笑)。私としてはこれまでにない形で登場人物に思い入れしながら絵コンテを描いたように思える。
いつでも絵コンテ作業は楽しくて仕方なかったが、「東京ゴッドファーザーズ」のコンテは尚のこと楽しくて楽しくて、もう申し訳ないほどであった。
誰に対して申し訳ないんだかは分からないが。
03.4.11
決算2002-53
絵コンテの変化について記す前に、もう少しシナリオのことを書いておこう。登場人物のパーソナリティに比重を置いたからといって、前2作に比べ「東京ゴッド〜」の物語・構成部分が後退しているかというと、そういうわけでもない。
私が話を作る際には構成をたいへん重要に考えているし、どうやら生理的に「構成」とか「構造」を考えるのが好きらしい。
ただ今回は表面上、アクロバティックな構成や展開は見られない。
情動と論理のパズルはちょっと飽きた(笑)
しかし、多層的な構造は違う形でシナリオや画面に現れている。
今回は「異界」ということを意識している。異界といっても、それとはっきり分かるような異世界ではなく、日常に重なる異界である。それも目で見るだけで
は半分も分からない異界である。これは完成した作品を見てもらう以外にないと思うが、シナリオ的な部分で言うなら、「東京ゴッド〜」における異界は、「意
味のある偶然が磁場のように強く作用している世界」といえようか。
「東京ゴッド〜」の世界観は次々と連続して起こる「ウソのような偶然と奇跡に彩られている」ということになるのだが、これはしかし非常に危ういバランスに
成り立っている。「東京ゴッド〜」の企画書に添付した、いわば監督ノート「意味のある偶然の一致にあふれた世界」という拙文にこんなことを書いている。
劇中内で流れる時間はわずか数日。一人の人間が、一生かかっても体験できるかどうかといった数々の劇的な場面をその短い期間に圧縮して見せる。当然普通では考えられない偶然が連続して起こることになります。
通常の作劇において、“偶然”というのは避けねばならないお約束事になっています。当たり前です。たまたま街で出会った人間が探し求めた仇であった日に
はご都合主義もいい加減にしろと、頭の悪い客ですら思うでしょう。“偶然見た”“偶然出会った”“偶然知った”“偶然拾った”などなど、こうしたご都合主
義の偶然は劇中世界の緊張感を失わせ観客から緊張感を奪います。しかしです。逆に偶然ばかりを集めてみれば面白い世界が出来上がる、そうした観点でこの作
品は作りたいと思います。もちろんただの偶然ばかりを繋げてもそれはでたらめの烙印を押されるのが関の山。ではでたらめではなく不思議な物語とするにはど
うするのか。モザイクのように並んだ数々の偶然や出来事をどうやって関連づけ意味を持たせるのか。そこに“因果”という媒介が必要になります。話は西洋近
代合理主義の束縛から離れねばなりません。
要するに「東京ゴッドファーザーズ」は「御都合主義の出来すぎた話」なのである。そこにリアリティ、というより説得力を持たせるには引用中にもあった通
り、出来事や人物を相互に関連づける「因果」が必要であり、この目に見えぬ、そして西洋近代的な意味ではない因果律こそが「異界」を形作っている。いる。
いる筈。そうなるようにしたつもりである。
03.4.14
決算2002-54
実は「御都合主義の出来すぎた話」というコンセプトは、元々アニメーションではなく、実写で作ったら面白いのではないかと考えていたものである。そんなアイディアをあえてアニメーションで作ろうと思った背景には、実は何もない(笑)
他にコンセプトがなかったわけではないのだが、気が付くとこれ以外に作る気にならなくなっていた、としか言いようがない。自分の乗り気に水をかけるような真似はしない。
「パーフェクトブルー」完成後、国内外を問わず多くのインタビューでうんざりするほど「何故実写ではないのか?」と聞かれた。この言葉には「実写でも出来るようなリアルな内容」というニュアンスが付帯していた。私にはいまもってさっぱり分からない。
この背景にはあまねく世の中を覆っている、「アニメは子供が見るものである」「実写はアニメより高級である」といった「おやくそくごと」があるように思われてならない。
話は逸れるが、「アニメは子供が見るものである」というのも困ったもので、この頑迷固陋な思い込みがあるがゆえ、特に「セックスと暴力」描写が糾弾され
るのであろう。いい年をした人間が電車で平然と漫画を読むようになっているというのに、アニメだけが子供向けである必要はどこにもないだろうに。もっと
も、「いい年をした人間が電車で平然と漫画を読む」のも批判の対象になりやすいのだが。
得てしてこうだ。
「いい年をした人間が電車で平然と漫画を読むような国は他にはない」
だからみっともない、というのだろうし、私もいい年をした人間が電車で平然と漫画を読む姿は好ましくないと思う方だが、しかし「外国にそういう例がない
からみっともない」という論法の方がよほどみっともないように思える。なぜ外国に比べねばならないのか。「日本の文化や歴史を大切にしよう」などともっと
もらしいことを口にする人間が、結局は外国からの、それも西欧文化圏を手本にした考え方、舶来の考え方しかしておらず、そのことを露ほども疑う頭を持って
いない。そんな「自称見識ある人々」の何と多いことか。
とはいえ、仏教や儒教といった舶来の物の考え方を風土に合う形で変形しつつ倫理、道徳観を形成してきたのが伝統なのだから、そうした西欧にならうことこそが日本の伝統の顕れなのかもしれないが。
「セックスと暴力」描写の横行は褒められたものではないだろうが、「セックスと暴力」に興味を持つのはごく当たり前のことであろう。
隠すがゆえに歪になることの方が余程問題にも思える。
「自称見識ある人々」が一番「セックスと暴力描写」を見せたくない「子供たち」こそが、実は一番「セックスと暴力」を見たいと思っているはずで、少なくともかつて「子供」を経験した私は強くそう思う。
時代が変われど子供の内面にさほど変化はなかろうし、昔の子供がよく遊んだ「チャンバラごっこ」、これはさも子供の健全な遊びのようにいわれるが、暴力
への興味と欲求に裏打ちされているのは明らかではないのか。刀をはじめ、鉄砲や戦車や戦闘機に憧れ、それらの絵を好んで描いたり模型を作るのも暴力的なも
の、広く言えば「力」への憧憬の顕れといえよう。人間は権力が好きな生き物である。
セックスだって同様であろう。みんな見たいのである、パンツの中味を。もう興味津々。だから見せて良い、見せた方が良いとは決して思わないし、確かに子供に見せるものについてはエロも暴力表現も規制を加えた方が良いとは思う。
ただ、子供のことはともかく、成人やその予備軍はエロもグロを見たがるもので、いつの世も需要と供給が成り立っている。「自称見識ある人々」が指す現代
のエロの醜悪さと、たとえば江戸時代の春画に描かれる巨大な男根や陰毛ボーボー、肉ひだビラビラのグロテスクさに大差はないだろうし、その表現の背後にあ
るものはイコールの筈だ。
それとも時を経たから「春画はアートである」というのであろうか。
現代だからグロテスクなのではなく、いつの時代にもそうしたものを好む傾向に違いはあるまいし、下手に抑圧しすぎればどんな形で暴発するか分からない。現代はもう少し抑圧しても大丈夫だと思うが。
私自身は特にグロテスクや醜悪を好むわけではないが、そうしたものを好む個人の趣味まで否定するつもりはなく、また矛盾ではなく「醜悪な美」ということも当然ありえると思っている。瓢箪から駒が出ないとも限らない。
時代が違ったところで「セックスと暴力」に対する欲求に変わりがあろうが筈がない。当然いつだってそうした需要も多かろうし、そういうものを作りたい人
間も多かろう。そればかりが横行する風潮にはうんざりはするが、私はむしろ、なぜもっときちんと「セックスと暴力」を描かないのか、と思う方である。
どうせ描くならチンピラみたいな「セックスと暴力」描写ではなく、もっと根元的なものに迫る「セックスと暴力」描写をすれば良いのではないかと思ってい
る。そういうものなら見たいではないか。映画「わらの犬」(監督/サム・ペキンパー)などは暴力を扱った芸術的な映画になっているではないか。私は大好き
な映画だ。
「セックスと暴力」描写を不健全のひとまとめに括って「正しくないもの」「悪いもの」と断罪するのはよほど簡単であろうが、そうしたものの考えの方が余程
危険に思われる。違う考えは排除すればよい、という至って単純な子供じみた理屈が行き着く先はイラク戦争に見る通り。
「自称見識ある人々」とどこかの大統領とは根が一つなのかもしれない。ああ、怖い怖い。
思い付きを並べているので、話題があちらこちらと転じている。
しかし「セックスと暴力」問題と同じで、私の作品に対して「なぜ実写ではないのか?」と問う姿勢の背後には「リアルなものを描くのは実写であるべき」という前提や「実写はアニメより高級である」という大変暴力的な前提が横たわっている。
そうした前提が大勢であるのはよく理解しているが、少数派の価値観を認めない大勢の考え方はやはりグローバルスタンダードという名の思想統制と同じである。ああ、怖い怖い。
03.4.15
決算2002-55
「東京ゴッドファーザーズ」の話であった。「御都合主義の出来すぎた話」というコンセプトの話題に戻る。
「パーフェクトブルー」公開後、実写を撮らないかという誘いが一度あった。あまりその気はなかったのだが、実写を撮るとしたらどういうものになるか、漠然
と考えたりもした。実際ネタも思いついた。このネタはもちろん「東京ゴッド〜」ではなく、まったく別の話である。内容は教えないが、作ればきっと面白い。
多分「卑怯だ」と言われるが。ちょっと「パーフェクトブルー」に似過ぎているが、実写にアニメを交えた実に「変な」ネタである。
それはともかく、本業のアニメーション作品が不本意なほどにリアルリアルと言われていたので、実写という見かけ上リアルな方法をとるのなら内容はまった
く逆に冗談みたいにリアリティがない方が面白いのではないか、と考えていた。ギャップが好きである。それに日々ニュースや新聞で伝え聞く現実の方がよほど
良くできた冗談のようであり、その冗談のような現実がそのまま反映される方が遙かにリアルというものではないか、とも思った。もちろんリアルなら良い、と
思っているわけではないが。
「見かけ上リアルな方法」だからギャップとして成立するはずだった「御都合主義の出来すぎた話」、このアイディアをアニメーションに持ち込んだ時点でコン
セプトとしては根底から成り立たなくなってしまった。そういう事情もあって今回は芝居の魅力がクローズアップされ、美術背景の写実性が重要になっている。
|